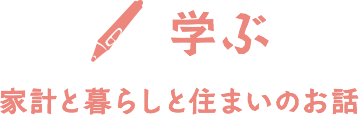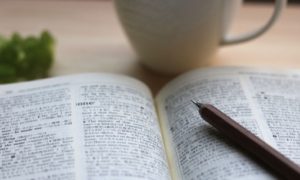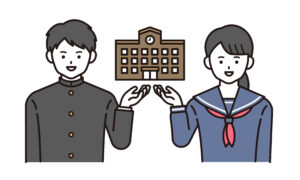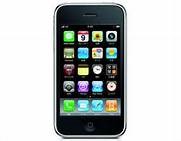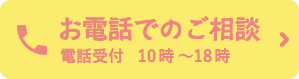金融リテラシーを身につけるためには?
2025/06/02 夢とお金
2022年に当時の岸田内閣から「資産所得倍増プラン」が発表され、金融リテラシーの向上と金融経済教育の充実ということがその中に盛り込まれて以降、「金融リテラシー」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。NISA制度やiDeCoの制度拡充も相まってより加速していると思います。そこで金融リテラシーをどうやって身につけるか私なりに考えてみました。
目次
1.金融リテラシーと金融経済教育について
金融庁の外郭団体である金融経済教育機構(略称J-FLEC)によれば、金融リテラシーの定義は「経済的に自立し、より良い生活を送るために必要な『お金に関する知識や判断力』のこと」とされています。そしてこの『お金に関する知識や判断力』を向上させるのが金融経済教育の役割とされています。これを推し進めるJ-FLECは、令和10年度末をめどに「金融経済教育を受けたと認識している割合」が米国並みの20%となることをめざす、と宣言したのです。(金融広報委員会金融リテラシー調査2022年によれば、7%程度)
それに合わせて、2022年度から高等学校の家庭科(「家庭総合」、「家庭基礎」という科目)や新科目の「公共」で家計管理・計画、リスク管理、ライフプランの基本を学び、さらに資産形成・金融商品については株式、債券、投資信託等の基本的知識を身につけ、資産運用の基本的意義を理解させる学習がスタートしたそうです。
少し内容にふれてみると、
- 使う ・・・・・・家計管理とライフプラニングについて
- 備える・・・・・・公的保険制度と民間保険
- 貯める、増やす・・金融商品を活用した資産形成
- 借りる・・・・・・リボ払いや分割払い、ローンなど
ということを扱っているようです。60代半ば過ぎの私が高校時代の頃とはかなり違っていることがわかります。
お子さんがいらっしゃる方は一度教科書を手に取ってはいかがでしょうか?
2.経験を積む重要性
このように重要な金融リテラシーですが、それがどうやって身につくのか考えてみました。私自身は「こづかい」を通じて何かしらの金銭感覚を身につけたと思います。毎日または毎週、10円あるいは50円くらいを親からもらい、それで駄菓子を買う、あるいは貯めて近くのおもちゃ屋へ行きプラモデルを買うという行為です。友だちと一緒にお店に行くことでA君は自分よりもこづかいを沢山もらっているということに気づくこともありました。さらに、お年玉などまとまったお金を貯金して高価なものを買うということを身につけましたし、その際貯金をすると少しずつ利息がつき残高がふえていくことも学びました。
大学4年間でアルバイトを通じてお金を稼ぐことの難しさや大変さを実感しました。授業料と食費(私は自宅通学)は除いて身の回りのものやクラブ活動で要する費用は家庭教師のアルバイトでまかない、足りない部分は貯金を取り崩していました。
卒業し社会人になると就職、結婚、子育て、マイホーム購入などのライフイベントを通じて住宅ローン、社内預金、生命保険、学資保険、持株会、財形貯蓄、等の知識や仕組みを習得しました。会社から体系だった説明もありましたが、必要に応じてこちらが尋ねる、またわからないときはその方面にくわしい社内の先輩や同期に話を聴きながらそのつど理解していきました。転勤のため最初の自宅を売却した際、かなりのローンが残ってしまいました。ただ、この時売却と同時に住まいを買い替えたことで「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」という他人があまり経験しない特例制度を学ぶことになりました。
勤務先の会社が何度も合理化したり、自分が所属していた事業部を分社化したりしたため、不安な気持ちがよぎったこともあります。しかし、先輩方が退職金の話をしていた時に何となく自分もこれくらいかと想像できたこともあり、50歳を超えると老後について何とか乗り切れるという気持ちに傾いてきました。
60歳に到達する前に、かつて取得した2級FP技能士を少しずつ復習して、親からの相続対応、厚生年金や退職金の出口戦略を考えるようになりました。一人では手に負えない相続は懇意にしている税理士に手続きをお任せもしました。
2005年に取得したFPの知識に上記のようなライフイベント経験がプラスされた結果、金融リテラシーが何とか身についたと実感しています。
3.金融リテラシーを身につけるためには
現在、上記の高等学校の授業をはじめ、企業やさまざまな場所で金融リテラシーを身につけるためのしくみや制度が用意されています。3年前にある高校で「奨学金のしくみ」を生徒の前で話したことがあります。その時に、奨学金を利用するということは生徒自身が契約当事者になること、お金を借りるとはどういうことか、そして計画的に返済することの重要性にふれて話をしました。奨学金の利用を通して金融リテラシーを身につける実践にもなるのではないかと思います。終了後先生と雑談をする機会がありましたが、「今の生徒たちはキャッシュレスが当たり前なので、いくら使ったという感覚がなく、歯止めがきかない。家庭での保護者との会話も重要で学校教育だけでは限界がある。」とおっしゃっていました。先生方の悩みは尽きないようです。
他方、周りをみまわしてもお金に関する動画が配信され、金融商品や資産運用に関するホームページも簡単に検索できます。しかし、その中には間違いや誤解を生む内容も含まれています。それらを正しく理解し、正誤を判断することはかなり難しい場合もあります。それを反映するかのように投資詐欺の件数と被害額はますます増えているとのマスコミ報道もあります。
学ぶことももちろん大切ですが、気軽に相談できる相手がいるか否かが大事だと思うようになりました。相談した時は「そんなことも知らないの」と言われたりもしましたが『聞くは一時の恥。聞かぬは一生の恥。』というか「一生の損」です。お金の話を気軽に相談できる相手や仲間がいて、初めて金融リテラシーの向上を実感できるような気がします。
以上述べてきましたように、金融リテラシーは重要です。それと同じくらいに経験(住宅購入、DC制度利用、株式購入などの資産運用等)も必要です。そして気軽に相談できる相手、これが一番重要かもしれません。最後になりましたが、もし、まわりに信頼できるそして気軽に相談できる仲間や相手がいなければ、一歩踏み出して日本ライフプラン研究所の扉を開いてみませんか?
フィナンシャルプランナー 米村 健史