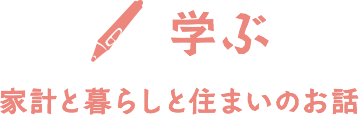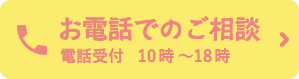思春期を楽しむ
2025/05/19 保険
子育てを始めた頃、子どもの成長を楽しみだと思う心のどこかで、思春期に対する漠然とした不安を抱いていたように思います。
自分の思春期はどうだったかというと、怖い父親に反抗できなかった私は、やりたいことのあれもこれもガマンし、たまにこっそり冒険してみると、すぐに見つかりもっと厳しく行動を制限されてしまうという情けない子でした。
ところが生まれてきたわが子は、私と違いしっかりと自己主張をし、やりたいことは何が何でもやってしまうタイプ。この子が思春期を迎えた時、あんなことが起きたらどうしよう、こんなことをされたらどうしようと、起きてもいないことをあれこれ考え、勝手に恐怖を覚えていました。
目次
思春期の特徴
思春期は、体の変化も心の変化も著しい。また、それまでは自分中心だった意識が、外の世界に向き始める時期です。つまりそれまでは何も感じていなかったことに対して、急に視野が広がりだし、批判の目が育ってきます。親や先生など周囲の大人に対して、それまで感じなかった気持ちを感じてしまう。つまり、「それって、人としてどうなのよ!」という目で見てしまうということ。そして同じ目で自分を見つめ自己嫌悪に陥ってしまうという、大変な状態になっているのです。
その上、異性にも目が向き始めます。自信を持ったり自信を失ったり、とにかく身も心も取り込み中なのです。
そんな時に親が今まで通りに接してもうまくいきません。ましてや親の威厳を損なってはいけないとばかりに、力でねじ伏せようとすると、エネルギーのない子はやる気を無くしていき、エネルギーのある子は、ますます反抗心を強くします。
これでは、なにをやっても良い結果は得られません。
思春期は反抗期?
思春期を表す「反抗期」という言葉がありますが、この言葉は大人の側から一方的につけられた言葉だなと感じます。つまり「私の言うことをききなさい」という意識が根底にあるということ。自我が芽生え始め、「できる」「できない」に関わらず、自分のことは自分で何でも思い通りにしたいと思っている彼らに、「親の言うことを聞きなさい」というのは、そもそも無理な話。反抗しない子であっても、不機嫌な態度をとられてしまいます。
ところで、「反抗」の反対は何でしょうか。
「素直」?「従順」?
「反抗」の反対、それは「自立(自律)」です。
大人になって大事なことは、自分自身で感じ、考え、選択決断をし、その結果を引き受けることです。つまり「自立(自律)」です。私たちは、そのために子育てをしているのですから、その子どもの気持ちを大切にしながら接することがとても重要なのです。
思春期の子どもとのコミュニケーション
思春期の子どもに対しては、ゆれる気持ちを共感的に聴きながら、あるいは、話さなくともしっかり見守っていくことです。
親が子どもに「疑心暗鬼」の目を向けているのか、「信頼」の目を向けているのか、子どもには正しく伝わります。
子どもの行動にいちいち「指示・命令」を出すのではなく、信頼して任せているのであれば、子どもにも「責任」の気持ちが育ちます。信頼関係のある親子であれば、必要になれば子どもの方から相談を持ちかけてきます。
そんな時でも、いきなりのアドバイスではなく「君は、どう考えているの?」ということ、そして「お母さん(お父さん)は、~と思うよ」という言い方であれば、「それは、私の考えと違う」とか「そんな考え方もあるんだね」という具合に議論が深まっていきます。そんな会話から、子どもの思いがけない一面が見られたりします。
どんなことでもちゃんと聴いてくれるという安心感が、子どもたちの大きな心の支えにもなるのです。
そうやって関わってみると、大人の入り口に立っている子どもと話すのはとても楽しい時間となります。
子どもの思春期を親としてたっぷり楽しんでみてください。

親子のマネーカウンセラー 鶴田明子