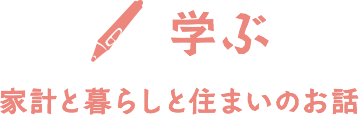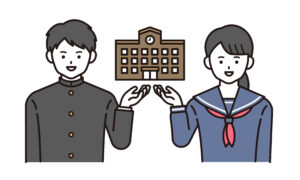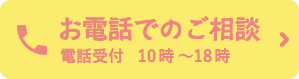幸せに生きるということ
2025/06/26 家族関係
目次
子育ての目的
「あなたの子育ての目的は何ですか?」子育て関連の講演会で、私がまず投げかける質問です。
私は『保護者がいなくても生きていけるように自立させること』だと思っています。
『親子関係』は死ぬまで続くもの。けれど、『子育て』は違います。いつかきちんと覚悟をもって、保護者の方が手を離していかなければなりません。そうでないと、子どもの自立が遠ざかります。
いつか終わらせないといけないと思っていると保護者の接し方も違ってきます。何でも自分で考えて、選択し、行動できるようにしなければならないのだから、保護者が手を出し、口を出し続けるとうまくいきません。
最近、その目的に『幸せに』という文言を追加しました。
つまり『保護者がいなくても幸せに生きていけるように自立させること』です。
そしてそのためには、『保護者が幸せでいて、子どもが自分の力で幸せになるのを見守る』ことが必要になってきます。
するとここでハタと心配になりました。
そもそも、今の日本の中で自立して生きている人は大勢いますが、「幸せ」を感じて生きている人はどのくらいいるのでしょう。
不安な社会
少子高齢化がすすみ、社会保障制度はさまざまな問題が明らかになってきています。年金制度の維持は長寿社会では重要なことです。それにも関わらず、先行きは不透明なままです。
日本の経済もなかなか上向きにならず、就職できない人や、不安定な雇用と低い賃金に苦しむ多くの人がいます。
地球温暖化のためなのか、異常気象も続いています。原発問題を始めとするエネルギー問題も深刻。
そして、年間自殺者が2万人という数字。一日平均50人以上が自ら命を断っているという事実に、私をとてもくらい気持ちになります。
こういう状況の中で、いったいどれほどの人が心から「自分は幸せだ。」と思っているのでしょうか。
自分を大切にするということ
ある本に、「幸せは、基本的に自分のことを認めている人が手にするものです。」と書いてありました。
つまり自尊感情が大きく関わってきているということ。日本人に大いに欠けている要素です。
大人も子どもも自分をもっと可愛がってあげましょう。
自分に厳しく、子どもに厳しくするのではなく、まず、優しくすることです。
家庭は『癒しと回復の場』になっていますか?
『しつけと教育の場』では、外で抱えたストレスを発散する場がなくなります。
学校、会社、PTAなど外の世界ではたくさんつらいことがあったとしても、せめて家庭の中だけは、くつろぎの場となるよう、心がけてみましょう。
その時に大切なのは、お互いの気持ちを「聴きあう」ことです。共感的に、「なるほど~、そうだったの。」という具合に。
そこにアドバイスは必要ありません。
一度この心地よい状態を味わえば、それがどれほどの幸福感をもたらすか理解できると思います。
無理をしなくてもありのままで大丈夫な場所がある。
それがあってはじめて外の世界で頑張れるのです。
そして、そういう状況でこそ「幸せ」が感じられるのだと、私は思います。

親子のマネーカウンセラー 鶴田明子